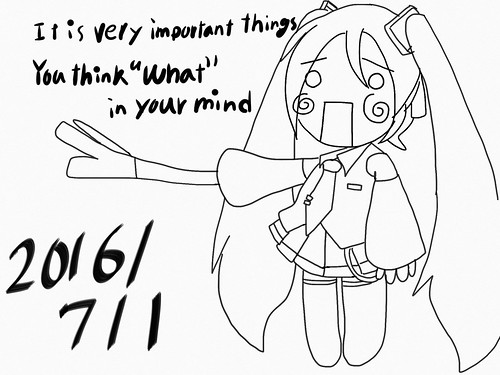よく授業中に「何か質問ありますか?」と教授や先生が言っている光景はよくあるだろうけど
これは別に何らかの儀式だとかルーティンというわけじゃないんですよね(そうでない人もいるとは思うけど)
そもそも授業の内容が理解できていなければ質問なんて浮かんでこない
ある意味これは真理というか、高校までの「わからないところはないですが」と大学のそれは(≒)ニアリーイコールではあるが、少し違います。
大学で何でテストの点数(通常ペーパーテストの回答は返却されません)がないかと言えば、そもそも大学であつかっている学問に一般的な正解というのは存在しないからです。
授業における基準として正解はあるのかもしれませんが、世の中でそれが普遍的であるということはないし、時代によって価値基準が異なるので今の所これが正解に近いのかもしれないくらいのもんでしかないでしょう。
普段パワーポイントだったり、板書に書かれていることを写しても質問が浮かんでこないというのは「必要最低限の部分しか講義で話してない」からだと思います。
特に文系の科目は単位がとりやすいとか色々あると思いますが、学習することが簡単ということはないです。
僕の場合は経営学を専攻してるので会計やら経済学やら色々やっていますが、授業外でまず書籍などに書かれている概念(フレームワークとか)を単語レベルで分解して暗記したり、テーマの中で類似するケースを調べたり(論文読んだり)、日常生活のどのシーンでそれが行われているのかとういうことを日々考えるくらいでやっとちょっとわかるレベルになりました。
もちろん経済分野なのでグラフを使ったり統計解析などで数学を使う機会があります。(すごく苦手な分野ではありますが)
なので、自分で学習する時間が長ければ長いほど、最低限の情報の中で話をされると抜けている部分はどうなっているのか質問したくなるんだと思います。
これは、学校という括りだけでなく日常生活においてもふと思いつく「なぜなのか」という疑問を大切にしている人は能力が高い傾向があるのと関係性は深いんじゃないでしょうか。
普段の適当に書いている日記なので詳しくはないですが今日の思った感想